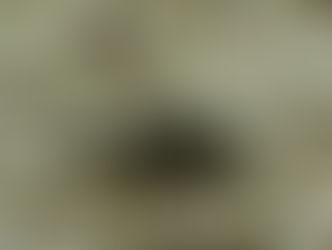

ナミツチスガリ
ハチ目 フシダカバチ科 体長 12~15mm コハナバチ類を狩るので、花の上でよく見られます。 踏み固められたような草の少ない裸地の地中に集団で巣をつくり、獲物をまとめて狩って巣の坑道に運び込んだ後で幼虫の育房を複数つくっていくといわれています。 ...


ヒゲナガハナノミ
コウチュウ目 ナガハナノミ科 体長 9~10mm 湿地周辺の草むらや林縁で見られます。 オスは触角がクシの歯状ですが、メスは鋸刃状でオスより黒っぽい色をしています。中には、真っ黒の個体もいます。 幼虫は湿地や水田の泥の中に生息し、尾の先が長い突起になっており、ここを水面か...


エグリトラカミキリ
コウチュウ目 カミキリムシ科 体長 9~13.5mm ガマズミやノリウツギなどの花に集まるほか、広葉樹の立ち枯れの木や伐採木にも集まります。 日本の北海道~九州と、朝鮮半島、中国、東南アジア、サハリンに分布します。 成虫は、5月~8月に見られます。 ...


アトジロサビカミキリ
コウチュウ目 カミキリムシ科 体長 7~11mm 里山の森林や都市部の緑地で普通に見られます。 クワ、アカメガシワなどの広葉樹やモミなどの針葉樹の枯れ枝や伐採木に集まり、樹皮や枯葉を食べます。 日本の北海道~九州と、台湾に分布します。 ...


ヤマサナエ
トンボ目 サナエトンボ科 体長 63~69mm 平地から低山地の緩やかな流れの川の流域に多く、溝や用水路のような小さな流れにも適応しています。 キイロサナエと大変よく似ていますが、オスは尾部の上下の付属器の先端の位置がほぼ同じになっていることで、メスは産卵弁が下方に突出し...


ヨツボシトンボ
トンボ目 トンボ科 体長 39~52mm 水の涸れない湿地や休耕田、抽水植物の豊富な池沼に生息します。 成虫は4月中旬~7月上旬に見られ、中でも5月に多く見られます。 日本特産亜種で、北海道~九州に分布します。 兵庫県内では、個体数が減少傾向にあるといわれています。...


カキノキ
ツツジ目 カキノキ科 落葉の高木で、高さは10mくらいになります。 中国西部の原産で奈良時代以前に渡来したという説と、山地に自生するカキノキの変種のヤマガキから日本でつくられたという説があります。 ヤマガキ自体も日本の在来種という説と中国原産という説があります。 ...


イボタノキ
シソ目 モクセイ科 高さ2~4mになる落葉の低木ですが、暖地では冬も緑の葉が残ることがあります。 日本の北海道~九州と、朝鮮半島、中国に分布します。 花は5月~6月に咲き、多くの昆虫がやってきます。 ライラックを栽培するときの接ぎ木の台木として使われます。 ...


ヤマウコギ
セリ目 ウコギ科 高さ2~4mの落葉低木で、森林や原野に生えます。 日本の固有種で、本州(岩手県以南)と四国(高知県)に分布します。 雌雄別株で、花は5月~6月に咲きます。 新芽は昔から山菜や救荒植物として利用されてきたもので、独特の香りがあっておひたしや天ぷらにして...


クロヒカゲ
チョウ目 タテハチョウ科 開張 45~55mm 雑木林周辺で見られ、樹液に集まります。 幼虫は、ササ類の葉を食べます。 日本の北海道~九州と、朝鮮半島、中国、台湾、サハリンに分布します。 成虫は、4月~10月に見られます。 (写真)2020.5.25 加東市畑























